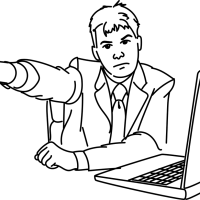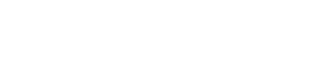そもそも休職制度は法律で認められているものではない!
ある労働者が傷病を負って労務の提供が不可能になった場合,使用者と労働者の労働契約はどのように処理されるかという点について,就業規則をしっかりと作成しているような会社の場合には「休職制度」が定められ,労働者の回復を待つ措置を採ることが多いといえます。
しかし,実はこの休職制度は法律に明確に定められているわけではなく,労働者の傷病が業務上のもの(労働災害)であった場合の解雇制限規定(労働基準法19条1項)以外には法律には何らの定めもありません。
そのため,休職期間を何ヶ月と定めるか,休職期間中の給与についてどのように取り扱うか,復職の可否判断をどのように行うかなどは,それぞれの労働契約,労働協約,就業規則などで定められることになります。ちなみに,休職中は無給である制度が多いと思いますが,この場合でも健康保険の傷病手当金をもらえるケースが多いでしょうから,いきなり生活できなくなるということはそれほど多くないと思われます。
休職制度というのは,本来,契約上の労働者の債務の本旨である労務提供ができなくなった労働者を直ちに解雇することを猶予する(回避する)ための制度であるといえます。
休職期間満了による退職とは?
上記のような傷病休職制度を就業規則に定めている会社では,従業員の私傷病による休職が一定期間継続し,復職の見込みがない場合に,「退職する」と定めていたり,「解雇する」と定めている場合があります。
まず,「解雇する」と定められている場合は,普通解雇の場合と同じように,それが解雇権の濫用といえるかどうかでその条項の適用の有効無効が決せられることになるのは分かりやすいと思います。そこでは,傷病の原因,休職期間,従業員の復職意思,復職可能性などを考慮して解雇の有効無効を判断することになります。特に,傷病の原因と復職可能性は重要な判断要素となるでしょう。
他方で,就業規則の定め方が「退職する」となっている場合は,解雇という言葉を用いず自動退職となるかのようですが,必ずしもそうなるわけではありません。むしろ,このような定め方をされていても労働者の就労意思と無関係に雇用契約を終了させるという意味においては「解雇」と同じように考えるべきでしょう。いわゆるエールフランス事件(東京地裁昭和59年1月29日判決)も,「右のような自然退職の規定は、休職期間満了時になお休職事由が消滅していない場合に、期間満了によって当然に復職となったと解したうえで改めて使用者が当該従業員を解雇するという迂遠の手続を回避するものとして合理性を有するもの」と述べています。
したがって,退職するという定めがあったとしても,自動退職となることが解雇権濫用法理を潜脱するようなことにならないように慎重な配慮が必要となり,特に復職可能性については慎重な検討が必要になるでしょう。
その意味で,「退職する」という規定であろうと,「解雇する」という規定であろうと,考慮すべき事情はほとんど変わらず,「退職する」という規定である方が有効と判断されやすいということもないと理解しておくべきでしょう。
最重要!復職可能性の判断
休職理由となった傷病が完全な私傷病である場合,休職期間満了による退職が有効かどうかで最も重要な要素は復職可能性です。この復職可能性は,実は2つの視点から考える必要があります。1つ目は純粋に「元の仕事に戻れるか」という視点であり,2つ目は「元の仕事には戻れないが他の職種であれば戻れるか」という視点です。この2つ目の視点が必要であることと同趣旨のことを述べた最高裁判例があります(片山組事件・最一小平成10年4月9日判決)。
休職期間満了による退職が争われるとき,1つ目の視点ばかりが争点になることがあるのですが,2つ目の視点も重要です。労働者側から見れば,主戦場で負けたとしても敗者復活のチャンスがあるということになります。ただし,労働者に別の職種でも復職したいという意思があることは大前提となるので注意してください。
復職可能性は誰が立証すべきか?
復職可能性があることの立証責任について,近時の裁判例では,解雇を猶予されていた労働者側にあるという傾向にありますが,いわゆる第一興商事件(東京地裁24年12月15日判決)は「企業における労働者の配置,異動の実情及び難易といった内部の事情についてまで,労働者が立証し尽くすのは現実問題として困難であるのが多いことからすれば,当該労働者において,配置される可能性がある業務について労務の提供をすることができることの立証がなされれば,休職事由が消滅したことについて事実上の推定が働くというべき」としています。これはつまり,労働者としては,「元の職種に復職できる」とか「あの職種であれば復職できる」という立証までしなくとも,「一般的職務について復職できる」という程度の立証がされれば,「休職事由が消滅したことについて事実上の推定が働く」ということです。事実上の推定が働くというのは,簡単にいえば立証責任が転換されるということです。
復職可否の判断基準は?
復職可否を判断するにあたっては,上記で述べた二つ目の視点までしっかりと検討しなければならならないことは,労働者側も会社側も注意すべきでしょう。このような考え方は,上記最高裁判例(片山組事件・最一小平成10年4月9日判決)の趣旨を敷衍したものといえます。
その判断基準について,より具体的に判示したものとして,東海旅客鉄道(退職)事件(大阪地裁平11年10月4日)があります。この事件で,裁判所は,復職可否の判断基準について,「労働者が職種や業務内容を限定せずに雇用契約を締結している場合においては,休職前の業務について労務の提供が十全にはできないとしても,その能力,経験,地位,使用者の規模や業種,その社員の配置や異動の実情,難易等を考慮して,配置替え等により現実に配置可能な業務の有無を検討し,これがある場合には,当該労働者に右配置可能な業務を指示すべきである。そして,当該労働者が復職後の職務を限定せずに復職の意思を示している場合には,使用者から指示される右配置可能な業務について労務の提供を申し出ているものというべきである。」としています。
したがって,会社側としては,職種や業務内容の限定がない労働者について,当該労働者が休職前の仕事に復帰できないとしても,使用者は配置可能な業務の有無を検討し,それがないというところまでしっかりと主張立証する必要があります。逆に,労働者側としては,「元の仕事に戻れます」ということだけでなく,「仮に元の仕事には戻れないとしても,他の一般的な仕事については戻れます」ということをしっかりと主張立証していく必要があります。
結局,休職期間満了による退職は争えるか?
結論としては,労働者が休職期間満了による退職は争えるかという点については,イエスということになります。会社側から見れば,仮に争われた場合でもその退職が不合理なものではないということをしっかりと主張立証するために,復職可能性を判断するプロセスをしっかりと取り入れ,他の配属可能性を検討した上で無理であると判断しておくべきということになります。
労働者側からすると,「自動退職の規定だからしょうがない」とか「元の職種に戻れないからしょうがない」と諦めるのではなく,「復職可能性がある」ということを医師の診断等の証拠に基づき主張立証していくことで,自動退職は無効だとして金銭補償を受けられる可能性が高まるといえます。